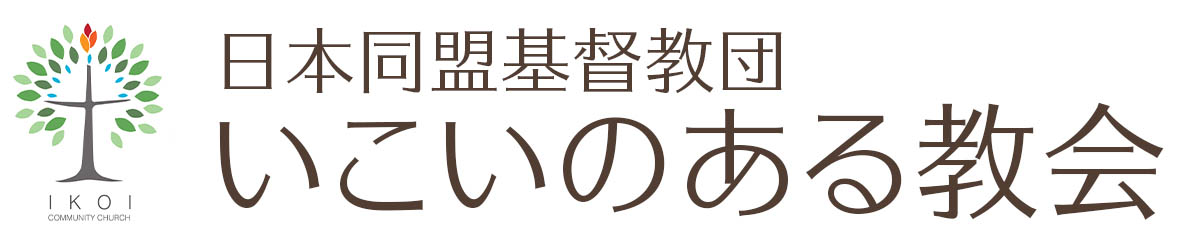先週の火曜日には東海西宣教区の先生方の集いである教師会が行われました。宣教区内の牧師たちの交わりと学びの場で、年に3〜4回ほど集まっています。毎回異なるテーマでの学びをしていますが、今回は「防災」について学び、考える時が与えられました。集まった場所は名古屋めぐみ教会でした。めぐみ教会周辺の地域は伊勢湾台風の時にも浸水した地域で、標高が低く、津波が起これば間違いなく浸水する地域だと言われているそうです。なので、教会では日頃から高い防災意識を持っていて、避難経路の確保、連絡体制の確立、被災後数ヶ月間のプランを考え、備えているそうです。
そのような学びをしながら、私たちの住んでいる地域に大きな地震が来たら教会として何ができるのかを考えてみました。最初に明確にすべきは、防災の備えはそれぞれの家庭ごとに準備すべきであるということです。教会はすべての教会家族のための非常食や飲み水などを確保しません。それぞれの家庭の事情に合わせて悩みつつ日頃からある程度の備えをしてください。
次に、教会として備えられる最低限のことは何かと考えた時、それは、被災した時に最も困ることを少しばかりお助けすることです。具体的には、飲み水の確保とトイレの提供です。水はポータブル浄水器を備えているので、必要なら川から水を汲み、きれいな飲み水にして使用することができます。もう一つ困るのがトイレです。被災したら断水しトイレが使用できず非常に困ったという被災地の体験談を聞きました。教会には非常用トイレ約100回分の備えがあります。年に1回ほど買い増しをしているので、もっと備えられるはずです。
最後は、教会員の安否の確認のための連絡網です。いこい家族はLINEグループでつながっているので、被災の際には速やかに安否確認をしていただき、助けが必要な方は具体的に記してください。被災した時にこそ、神の家族の繋がりを大切にし、助け合いながら共に困難を乗り越えていきましょう。